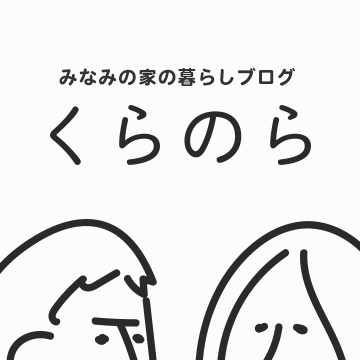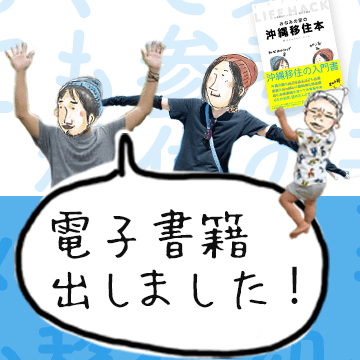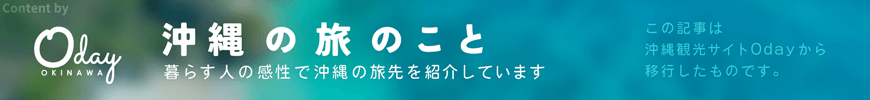
伊計島「イチの里 仲原遺跡」沖縄の縄文時代の竪穴式住居
※記事の情報は執筆時点のものとなります(9年前の投稿)
奥さんと仕事中に「これからは縄文がトレンド!スマート竪穴式住居なんて作ったら流行るんじゃない?笑」と、うさんくさい話をしていたら気分が乗ってきたので、竪穴式住居を調べたくなりました(実話)。
そういえば、沖縄にもそんなのあるのかなぁ、なんて検索してみたらあるんですね、実際。
- スポンサーリンク
イチハナリに残る縄文の跡
うるま市伊計島。「イチハナリ(一番離れた島)」と呼ばれるのどかな島に「仲原遺跡」はあります。

縄文時代の人々の住居跡が見つかった場所だそうです。
仲原遺跡(なかばるいせき)は、沖縄県の伊計島にある縄文時代晩期~弥生時代前期(沖縄貝塚時代中期)にかけての村落跡である。所在地は、沖縄県うるま市与那城伊計。
縄文時代後期(約2500年前-2100年前:沖縄貝塚時代中期)の沖縄県の代表的な村落跡である。
引用:仲原遺跡 – Wikipedia より
1986年に国の史跡に指定されたそう。
ドライブがてら行ってみました
現在、うるま市に住んでいる私たち。
伊計島に車で行くのもそんなに遠くなさそうだったので、ドライブがてら向かってみました。

じゃじゃん!到着!こちらが入り口。わかりやすく縄文ですね〜。

入り口の向こうにはすでに、復元された住居たちが見えます。
管理人さんがいたり、入場券を買ったりすることはないようです。きちんと整備はされていますが、公共の広場といった感じです。

あら、「ハブに注意」の看板が。いるんですね。
遺跡内は基本的に開けているのでいなそうですが、草の茂みや近隣の畑には入らないように注意しましょう。

仲原遺跡の概要が書かれた碑を発見しました。
仲原遺跡は、島のほぼ中央部の平地に営まれた縄文時代のムラの跡です。北側海岸に近年まで利用されていた自然湧水(インナガー)があり、縄文時代から使われていたものと考えられます。遺跡一帯はもとキビ畑で、土地改良事業の事前の発掘調査で竪穴式住居址が発見されました。これにより不明であった沖縄県の縄文時代晩期(約2500〜2000年前)のムラの広がりや住居の大きさ、造りなどが具体的に分かってきました。また遺物も土器の鉢、壺、石斧類、骨製の針、甕、他に当時の人が食べ残した獣、魚骨類、貝殻類が出土しました。
引用:仲原遺跡の概要より
ここの遺跡が発見されて、沖縄の縄文時代のことがわかりだしたようです。貴重な場所です。
竪穴式住居を観察してみる

さて、こちらが竪穴式住居。結構おっきいんですね。

住居によってサイズもまちまちでしたが、一番大きいサイズの家と、私(身長165cm)と比べるとこれくらい。

第15号復元住居だそうです。

どれどれ、中はどうなっているのかしら?

おぉー!木でしっかりと屋根と柱が組まれてますね!壁も石が積まれていて結構しっかりしています。
復元とはいえ、縄文時代もなかなか工夫を凝らして家を作っていたのでしょうね。

とはいえ、床に目をやると、ここ最近の雨で水たまりができていました…。
竪穴式住居は、地面に穴を掘って、その上に屋根を付けるだけなので、雨が降ると浸水してしまうのでしょうね。大変だ。
うーん、さすがにこれをスマート竪穴式住居とうたうのは厳しそうです笑
竪穴式住居の骨子もある
向こうを見てみると、何やら他とは変わった住居が。

何でしょう、あの骨のような家は。

どうやら、竪穴式住居の柱の骨子のようです。藁葺き屋根にする前のもの。

縄文時代でも、木同士をうまく紐で縛って固定していたんですね。技術力があるなぁ。

竪穴式住居は中に入れなかったのですが、ここだけ中に入れたので、ためしに入ってみます。
人が一人、寝転がって暮らすくらいのサイズ感。今でいうとテントみたいなものですね。

一応、立つこともできます。
いやはや、こんな場所で寝泊まりしながら島で生活していたなんて思うと、なかなか暮らしも大変だったんだろうなぁと思います。でも考えようによっては、沖縄の自然の真っ只中で暮らすなんて、縄文はロマンある生活だったのかもしれません。

向こうには海。いやぁ、何だか縄文時代にタイムスリップした気分です。
昔の暮らしを想像できるのんびりした時間
縄文暮らしを想像しながら、実際に復元された住居を見られるのはいいですね。
仲原遺跡は広場みたいなものなので、10分もあれば見られます。伊計島に行った際は、休憩がてら寄ってみるのもいいかもしれません。

最後に奥さんが「ヒミコ様ぁ〜!」と一発ギャグをやってくれましたが、これは弥生・古墳時代ですね。
お後がよろしいようで。

それでは、お家(竪穴式住居)へ帰ります。
そんじゃーね!